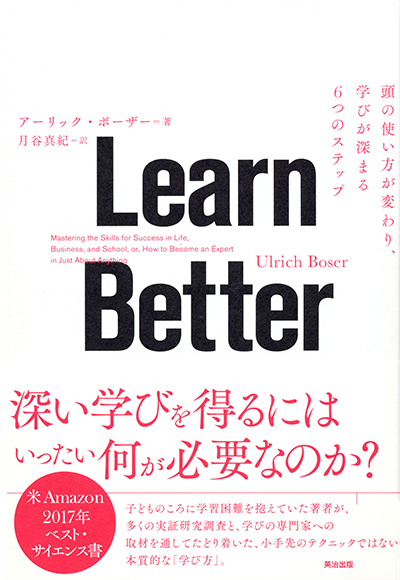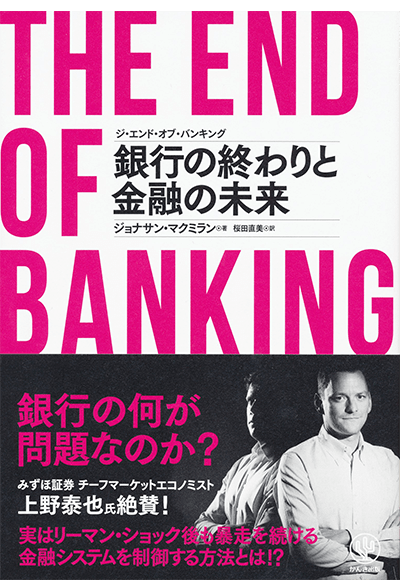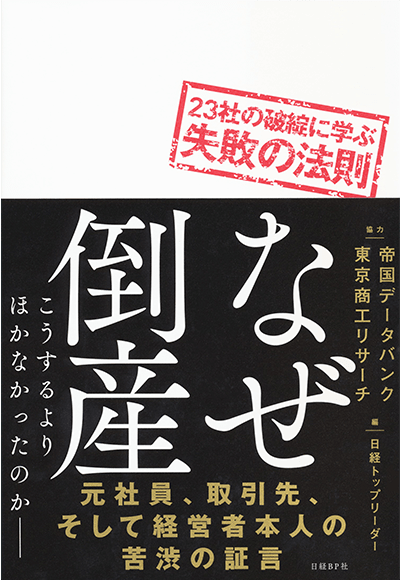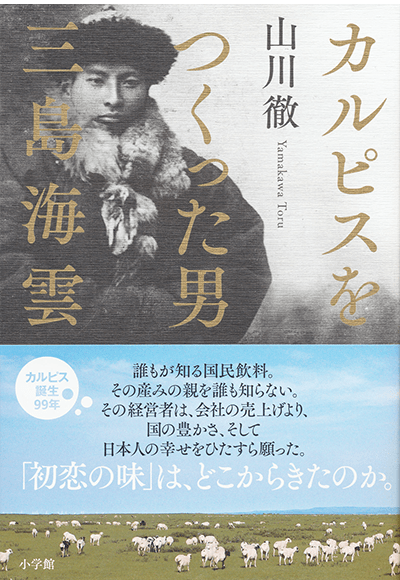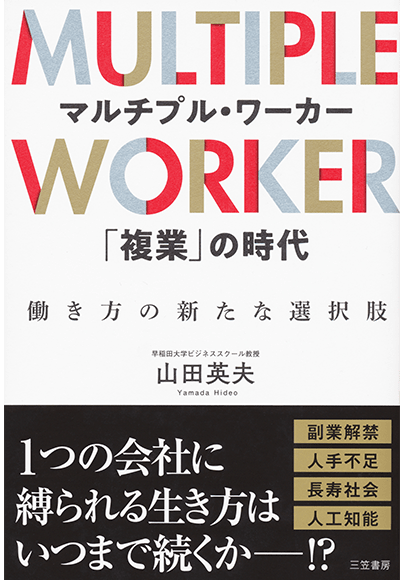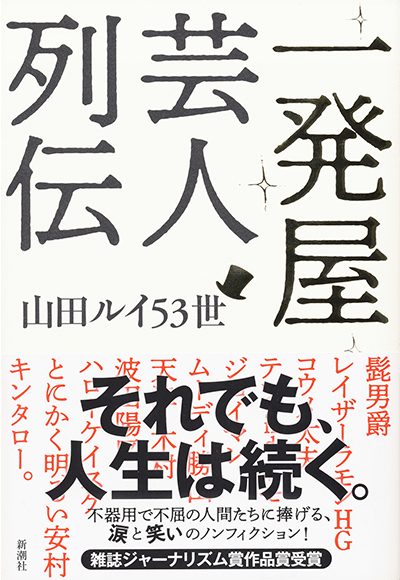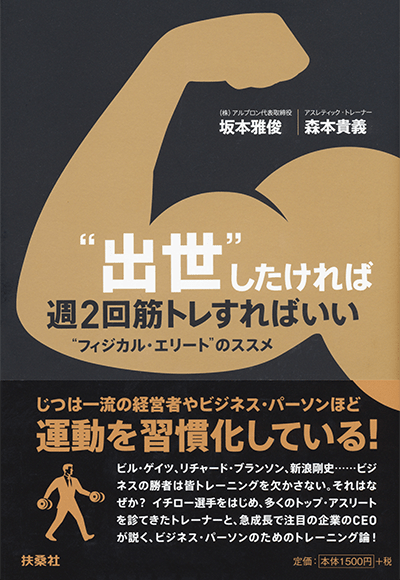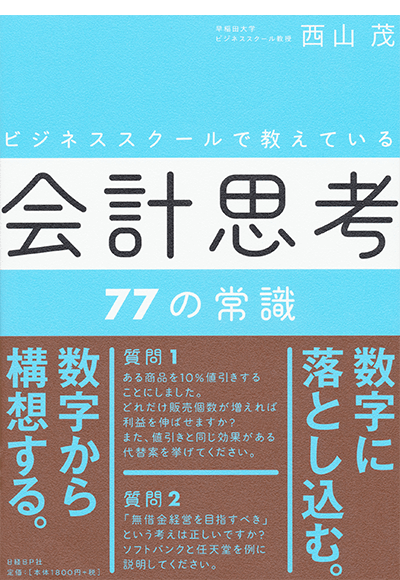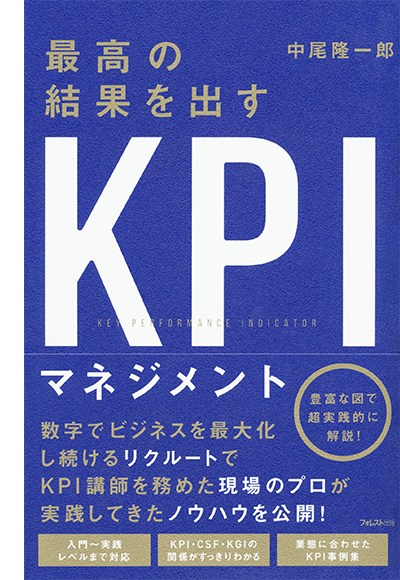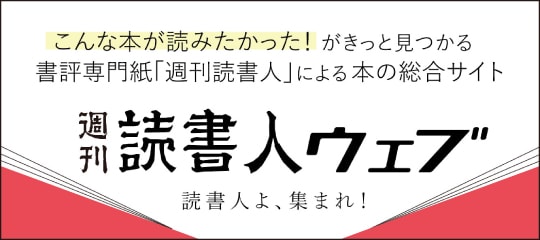2018年10月の『視野を広げる必読書』
公共の「広場」に生まれ変わった銀座ソニービル
先日、仕事帰りに「銀座ソニーパーク」(以下、ソニーパーク)に立ち寄ってみた。2018年8月にオープンしたこの“公園”は、2017年3月末に営業を終了したソニービルの跡地に造られている。
銀座のランドマークの1つとして1966年の開業から約50年にわたり親しまれたソニービル。地上8階地下5階の威容を誇る複合ショールームビルだったが、現在のソニーパークは地下4階分を残したまま地上は平地になっている。ソニーパークのウェブサイトは、「地下に吹き抜けがあるオープンな垂直立体公園」と説明している。
私が訪れたのは平日夜、しかも雨天だったためか、来場者はまばらだった。各フロアに店舗は配置されているものの、全体にあえて「空白」を残した作りになっているようだ。
正直、少し寂しい印象を受けた。オープンからひと月ほどたったタイミングだったので、オープニングイベントなどが一巡したせいもあるのだろう、がらんとしている。だが、都心の一等地に空白を作ったソニーの潔さと、その空白を埋めるべく、これからさまざまな冒険や挑戦が行われていく可能性を感じることもできた。
地下に広がる公共の「広場」をめざしたのだという。誰でも、自由に休憩や待ち合わせに使用できる。地上部分には「アヲ GINZA TOKYO」があり、緑があふれている。ここは、プラントハンターの西畠清順氏がプロデュースした「買える公園」。同氏が世界中から集めた植物をその場で購入できる。買われることによって植栽が入れ替わるという仕掛けだ。
なお、この形態のソニーパークは2020年秋までで、その後2022年に「新ソニービル」を完成させる予定になっている。建物が新築されても、現在の広場としての機能は残されるようだ。
本書『ソニーは銀座でSONYになった』は、ソニービルの歴史を構想段階から追ったノンフィクション。著者の宮本喜一氏はソニーおよびマイクロソフトでマーケティングなどに携わった経験のあるジャーナリスト、翻訳家である。
ソニー製品の先進性や利便性を伝える日本初のショールームビル
ソニービルを構想し、計画の中心となったのは盛田昭夫氏。井深大氏とともにソニーの前身である東京通信工業を終戦直後の1946年に創立した人物だ。本書の物語は、盛田氏が副社長として社長の井深氏を支えていた1962年に始まる。
当時のソニーは、銀座に約35坪(約116平米)ほどのショールームを所有していた。ソニー企業という不動産管理会社を設立してまで、このわずかな土地にショールームを設けたのも、盛田氏の手腕によるものだった。
その頃のソニーの本社は東京・五反田にあり、その企業イメージは一等地の銀座とはかけ離れていた。だが、盛田氏は銀座進出にこだわった。これから世界を相手に勝負をかけるソニーならば、世界に知られる東京・銀座のイメージをまとうべきと考えたのだ。「ソニーと言えば銀座、銀座と言えばソニー」と呼ばれたかった。
さらに大きな土地を取得し、「銀座のソニー」を確立したかった盛田氏は、「ビル全体がショールーム」という当時としては斬新かつ大胆な発想にたどり着く。実現すれば日本初となる試みだった。
ショールームという概念すらまだ一般になじみのない時代に、ビル全体をショールームにしようというのだ。しかし、なぜショールームなのか。本書によれば、盛田氏も井深氏も、ショールームが「マーケットの創造」になると信じていたからだ。
つまり、最先端の、まだどこにもない製品を開発したところで、それがいかに高機能で良質なモノであったとしても、多くの人に買ってもらうのは難しい。一般の消費者にはどう使っていいかわからないからだ。ならば、メーカーの側から、製品の先進性や利便性を的確に消費者に伝える「場」が必要だ。それに最適なのが、ある程度の規模があるショールームなのだ。
つまり、後にソニービルとして実現する、日本初のショールームビルの目的は、ソニーブランドを発信し、マーケットを創造することにほかならない。ブランドの中身を伝えるのがショールームという形態であり、ブランドのイメージを植えつけるのが銀座という立地なのだろう。
グッゲンハイム美術館をヒントに「タテのプロムナード」を発想
さて、冒頭にソニーパークが公共の広場として計画されたことに触れたが、実はこの広場というコンセプトは、ソニービルの計画の中にもあった。
1963年初頭に、ソニー社内で、新しいビル計画に打ち込む建設委員会が組織される。しかし、最初は議論百出でなかなかまとまらない。全員が納得する案がまったく出てこなかった。そこで、盛田氏は人数を絞り、ホテルオークラの1室を借りて徹夜覚悟の徹底的な議論を行うことにした。参加したのは盛田氏を含む5人。その中には、ビルの設計を任された建築家の芦原義信氏もいた。
ソニーに限定せず、同社を核としてさまざまな企業が出店する総合的なショールームビルにする、というアイデアが浮上し、まとまりかけた頃合いに、盛田氏がふとある思いつきを口にする。ニューヨークのグッゲンハイム美術館がヒントになるのではないか、というものだった。
グッゲンハイム美術館をご存じの方はどれくらいいるだろうか。丸い渦巻き状の特徴的な8階建ての建物には「白いかたつむり」というニックネームがある。建物の中央部が吹き抜けになっており、その周りに上から下まで、渦巻き状のスロープがある。訪れた人はエレベーターで最上階に上り、そのスロープを歩きながら展示作品を鑑賞する。すると、いつの間にか1階まで降りているのだ。散策するように歩みを進めながら美術作品を楽しめるというわけだ。
同様に各フロアの展示物を自然に見て回れるショールームビルにしてはどうか、という盛田氏のジャストアイデアにもっとも触発されたのが、設計者の芦原氏だったという。
話し合ううちに盛田氏から「タテのプロムナード(散歩道)」という言葉が発せられた。一方の芦原氏は、当時の日本にはほとんどなかった「街の中にある広場」といった公共的な空間を自らの設計に取り入れたいと、常々考えていたそうだ。
これらの発想が、後にソニービル最大の特徴の1つとなる「花びら構造」に結実する。芦原氏が提案したものだ。すなわち、各階の床を田の字型に4分割し、それぞれを真ん中の柱を中心に段違いに下げて設置する。そうすれば柱の周りをひと回りすることで1階分下がることになる。
予定されていた建築規模では、グッゲンハイム美術館のようなスロープを設置するスペースを取るのが難しい。ならば、フロアがらせん状に重ね合わさった形状にすれば、散策するような連続的な人の流れを作り出せるのではないか。それが芦原氏の画期的なアイデアだったのだ。
銀座ソニーパークは未来の「可能性」を“探す”空間
地下に広がる垂直立体公園である現在のソニーパークでは、吹き抜けがあり、扉や壁を極力少なくすることで、開放的な広場となる空間ができあがっている。地上からストレスなく、自然なかたちで地下の各フロアに下りていけるようにもなっている。
実際本書には、2013年、平井一夫ソニー社長から、ソニービル更新のためのプロジェクトのリーダーに指名された永野大輔氏が、「盛田氏の考えに立ち返った」という描写がある。芦原氏のアイデアを取り入れた盛田氏の「ソニービルは広場」という考えを、「公園」に発展させたのがソニーパークなのだという。
ただし、ソニーパークの場合、ショールームとしての機能は弱く、地下に広がるプロムナードで「見て回る」べきものはとても少ない。余白がたくさんあり、これからの可能性を秘めた空間なのだ。
であるならば、ソニーパークを歩きながら見て回るべきは、その可能性なのではないか。いや、見て回るというより「探す」空間であると言うべきか。
ネットメディアであるASCII.jpの2018年8月24日付の記事「銀座ソニーパークで本当にやりたいのはPlayStationやスマホと同じ役割」では、ソニーがソニーパークを「プラットフォーム」として位置づけていることを紹介している。記事タイトルにあるように、ソニーパークは、PlayStationやスマートフォンと同様のプラットフォームというわけだ。
プラットフォームとしてのソニーパークは、そこで出店したりイベントを開催したりするパートナー(ソニーパークの店舗はテナントではなくパートナーと呼ばれる)、そして訪れる人たちと一緒に、これから作り上げていくものなのだ。
これは、ソニーという企業の姿勢やビジョンを示すものと解釈してもよさそうだ。
ソニー、ひいては同社に代表される日本企業が今後どのような方向に進むべきか――。本書で「新しいもの」を生み出すべく粉骨砕身の努力をした人々の情熱に触れながら、そんなことに思いをめぐらせてみてはどうだろうか。

情報工場 チーフエディター 吉川 清史
東京都出身。早稲田大学第一文学部卒。出版社にて大学受験雑誌および書籍の編集に従事した後、広告代理店にて高等教育専門誌編集長に就任。2007年、創業間もない情報工場に参画。以来チーフエディターとしてSERENDIP、ひらめきブックレビューなどほぼすべての提供コンテンツの制作・編集に携わる。インディーズを中心とする音楽マニアでもあり、多忙の合間をぬって各地のライブハウスに出没。猫一匹とともに暮らす。